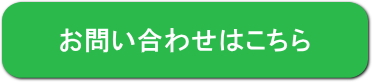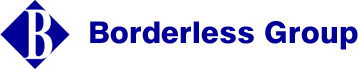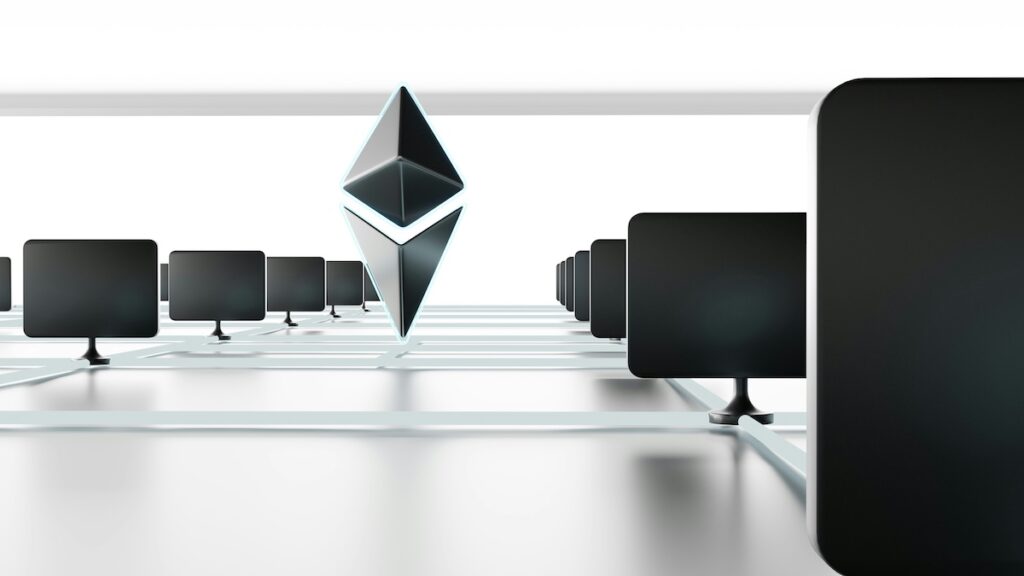
2024年11月のアメリカ・トランプ大統領の当選をきっかけに一気に価格を上げてきた暗号資産マーケット。2月中旬現在ではビットコインでピークから5%ぐらい下の水準を推移している。急騰した3ヶ月以上前から暗号資産を保有している人は大きな含み益が出ていることだろう。
そうでない人から見れば羨ましい限りだが、実は以前から持っていた暗号資産の価値が爆上がりした人たちは結構大きな悩みのタネがある。それは「税金」だ。
暗号資産と株式にかかる税金の違い
暗号資産は株式などの金融資産のようにチャートを刻みながら動き、安いところで買って高いところで売る、あるいは先物取引を使えば高いところで売って安いところで買い戻すことによって利益を得ることができる。株式は証券会社を通じて株式市場で取引するが、暗号資産は取引所を通じて売買ができる。やったことのある人ならよくわかるが、その取引の手軽さにおいては株式も暗号資産もさして変わらない。
しかし、獲得した利益に対する所得税の計算の仕方はまるで違う。株式の場合は売買によって得た利益(キャピタルゲイン)に対して、他の所得と切り離して分離課税として一律20.315%を所得税として支払うことになる。一方で暗号資産は雑所得という税目になり、これは給与等々の他の所得と合算して累進課税で所得税が徴収される。先の分離課税に対してこれは総合課税と呼ばれる。キャピタルゲイン税は一律だが、総合課税の方は累進なのでもちろん暗号資産の利益や給与等を合計した所得が小さければ20%以下になることもある。総合課税の方は課税所得695万円以下であれば税率はキャピタルゲイン税の20.315%を下回る。
ただ暗号資産マーケットが生んだ「億り人」という言葉が象徴するように一気に数億円の含み益を獲得した人も少なくない。そういう人たちは保有している暗号資産をを売却しようとすれば簡単に最高税率である国税45%、住民税10%の合計55%の所得税水準に達してしまう。株で同じ利益を獲得するのと比べて、30%以上も多く課税されてしまうのだ。自分で取引をして利益が出たのなら納税しても手元に半分近くは残るので、それで良しとするように情緒を調節するという解決方法はあるだろう。
特殊ケースでの暗号資産課税の災厄
しかし暗号資産の含み益のお陰で家族に災厄が降りかかることもある。大きな含み益を持った状態でその暗号資産の持ち主が死亡して相続が発生する場合である。もし数億円の含み益を持った人が亡くなった場合、相続人には55%の相続税の支払いがのしかかって来る。相続資産価値は相続開始時点の時価で計算される。その後相続の手続きがあり、相続税を支払うことになる。相続税は現金で支払わなければならないので、多くの場合相続した暗号資産を売却して現金を調達することになる。
ちなみに暗号資産は価格の上下の非常に激しい資産だ。そこそこの時間のかかる相続手続きの間に価格が大きく変わることもある。もしその間に暴落すれば最悪相続税の支払額を下回ってしまうこともある。そうして相続人が破産する、あるいは相続を放棄せざるを得ない状況は実際に発生しているようだ。もちろん価格は下がることもあれば上がることもある。価格が上がれば上がったで相続税の支払いのための売却で、また所得税もかかって二重の支払いに追われるということもあるらしい。
海外移住と暗号資産の節税
だが、不利・不公平なことばかりではない。暗号資産を取り巻く環境にはすこぶる有利なものがある。それは海外移住して、日本の非居住者になれば暗号資産の売却に関わる所得税の大幅に節税が可能であるということだ。海外に住んで一定条件を満たし、海外の居住者であるという認定を受けることができれば、その居住国の制度に従って現地で納税することになる。基本的にはどの国も暗号資産の利益にかかる税金は日本ほど高くない。ドバイや香港、シンガポール、マレーシアなどのように暗号資産の利益に対する税金がゼロという国もある。
一方で、株式の場合はそういうわけにはゆかない。2015年に施行された「出国税(国外転出時課税制度)」というものがあり、1億円以上の有価証券等(株式、投資信託、未決済デリバティブ取引など)を保有している人は海外移住する際に保有する有価証券等「みなし譲渡」扱いとなり、移住時点の時価で売却したと仮定して譲渡所得税が課されることになっているからだ。つまり暗号資産は国内で取り扱う場合はかなりので税負担があるが、海外へ移住することで100%節税ができるというかなりいびつな環境下に置かれている。
株式他の有価証券の場合は税制的にも有利な面は多いが、海外移住時にもある程度の負担を避けられないという側面がある。そういう制度のゆがみは「おかしい!」ということで、現在暗号資産の所得税を株式並みにするという議論は国会でも行われているようだ。ということは、同時に出国税に関しても暗号通貨は株式並に扱われる可能性があるということも視野に入れるべきだろう。法整備が追いついていないからこそ合法的に利用できるメリットは上手に活用するのが合理的なのは言うまでもない。